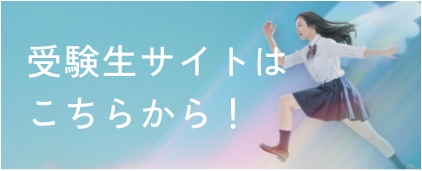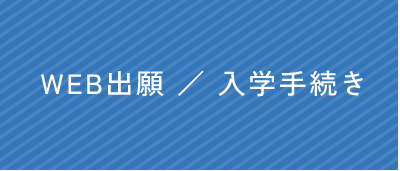羽衣TODAY
南海電鉄による「新規事業の取組と今後(第12回)」「データマーケティング戦略(第13回)」についてご講演いただきました(「地域開発論A」「現代社会学特別講義D」「放送メディア特別講義C」)
「地域開発論A」等(吉村宗隆先生担当)では、産学連携の一環として、南海電鉄が取り組む社会課題について現場の「生の声」に学ぶ授業を実施しています。毎回、南海グループ企業の様々な部署の方にお越し頂いており、第12回(12/11)は、イノベーション推進部の山崎寛司氏より「南海における新規事業の取組と今後」について、第13回(12/18)は、データマーケティング推進部の村上貴彦氏より「南海電鉄のデータマーケティング戦略」についてご講義がありました。
“第3の柱”となる新規事業の創造
本講義では、従来の鉄道会社のイメージを覆すような驚きが何度もありましたが、なかでも、ネパールのIT人財を紹介する「ジャパール」(第3回)やeスポーツ(第4回)は、開講して間もないこともあって、印象深かったのではないでしょうか?
これらの事業への取組は、南海電鉄が2022年度~2024年度の3か年計画として策定した中期経営計画「共創140計画」(→こちら)において、公共交通事業、まちづくり・不動産事業に続く“第3の柱”構築に向けた未来探索として位置づけられています。12・13回の講義も新規事業の創造に関する内容でした。
「南海における新規事業の取組と今後」(第12回)
・オンラインとオフラインとが同化する新しい世界での価値提供
講義の冒頭で南海電鉄の既存コア事業である2つの柱について触れた上で、山崎氏は「では、なぜイノベーションなのか?」と問い、その意義を次のように説明されました。
「南海電鉄がこれまで提供し続けてきた価値―人を送り届ける、人が集まる場所を作る、という価値―を世の中の変化に合わせてアップデートしていく必要があります。例えば、それは、オンラインとオフラインとが同化する新しい世界での価値提供です。」
この“オンラインとオフラインの同化”の例として、駅改札でのVisaのタッチ決済の導入(→こちら)や、事業提案制度「Fly beyond」(南海グループ社員が対象)(→こちら)によってスタートした新規事業、テニスコートの空き状況を一元的に検索し予約できるサービス「テニスグ!」(→こちら)等は、この“オンラインとオフラインの同化”を実感できる便利なサービスです。
2022年からは社外から新規事業のアイデアと人財を募り、事業化を目指す「beyond the Border」(→こちら)が設置されました。美味しさと栄養、食の楽しみを提供する“「創作精進料理のファストフード ”yuppa”」の実証実験が行われるなど(→こちら)、これまでの鉄道会社としてのイメージからますます自由に、ユニークな新規事業への挑戦が続いています。
「南海電鉄のデータマーケティング戦略」(第13回)
第13回講義の「データマーケティング」も前回に引き続いて“未来探索”の事業として位置付けられています。
南海沿線で生活する私たちは、知らないうちにデータマーケティングの恩恵を受けています。例えば、昨年12月に関空特急ラピートのダイヤが見直され、平日午等は関空~なんば間の停車駅が減り、速達性が向上しました(→こちら)。このダイヤ改正が可能になった背景には、乗降客のデータを分析するデータマーケティングの存在があります。
・事業横断的なデータ活用
村上氏はデータマーケティングが求められる背景として、(1)私鉄経営のビジネスモデルの転換、(2)マーケティング手法の転換を説明されました。
(1)1世紀以上続いてきた私鉄経営モデルー沿線のまちを開発することで乗客を創造するモデルが、人口減少など社会環境の変化によって、新しいビジネスモデルー顧客を起点としたモデルへと変革している。
(2)マーケティングの手法が、従来の交通・流通・不動産などの各事業部でバラバラに顧客にアプローチしていた方法からデータを事業横断的に活用できるようになり、顧客起点のサービス提供が可能になった。
・顧客起点のサービス
事業横断的なデータマーケティングによって、利用者はよりきめ細かなサービスを受けられるようになります。その好例と言えるのが、minapitaポイント(南海沿線での買物や鉄道利用でたまるポイント)(→こちら)をあまり使っていない会員に、一定額以上の買い物をすると復路の切符をプレゼントするというサービスで、店舗と鉄道双方の利用促進を可能にする事業横断的で顧客起点の施策です(→こちら)。