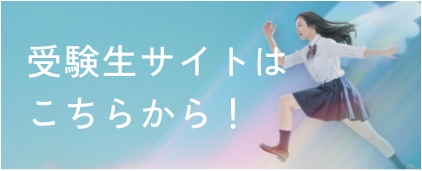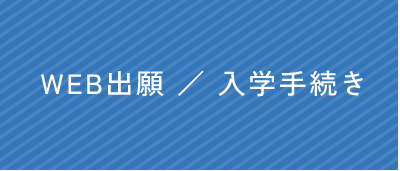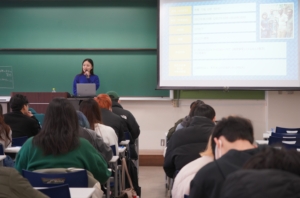高校生の頃、協力隊のポスターを見て国際協力に興味を持ったという佐賀氏。
大学生活ではオーストラリアやフィリピンへの留学やNGOのスタディツアーに積極的に参加されていました。
卒業後、食品メーカーで営業職として4年の勤務の後、26歳の時に自分のやりたいことを思い返し、海外でのボランティア活動を決意されました。
エチオピアはアフリカ大陸の北東に位置し、日本の3倍の国土に約1億人、88以上の民族が混在している国です。
民族性を反映した多種多様な服装も特徴的で、エチオピア正教においては白い布を纏うのが正装とされています。
これらの様子はアフリカをはじめとする世界の少数民族や先住民を撮影している写真家のヨシダナギ氏にも紹介されています。
エチオピア人の主食はイネ科の穀物「テフ」を自然発酵させてクレープ状に薄く伸ばして焼く「インジュラ」というもので、これにワットと呼ばれる肉や野菜の具材を包んで食べます。
発酵食品の為、酸味が強く某YouTubeチャンネルでは「見た目は雑巾、味はゲロ」と酷評をされていましたが、派遣後2年目には3食インジュラで問題なく過ごせたようです。
また、生肉を食べる文化についても触れ、祭事では友人宅の庭でさばいた生の牛肉が振る舞われたエピソードもお話しされていました。
主な産業はコーヒー豆の輸出で人口の1/5が生産に関わっているそうです。
また、生産されたコーヒー豆の国内消費率は1/3と言われるほどコーヒー文化は国民に愛されています。
ジャバナン(ポット)に湯を沸かし、挽いたコーヒー豆を濾す為とても味が濃いことが特徴で、路肩に皆で椅子を持ち合い、シニー(おちょこ)にいれて飲む風習があります。
地方のコミュニティは基本的に井戸水で生活をしており、バケツやハンドポンプを使用して水を汲みます。
片道1時間程かけて女子供が、時にはロバを使用して運搬するそうです。
佐賀氏はJICA海外協力隊として公衆衛生の面で現地の方を支える活動をされていました。
具体的には、JICAの水プロジェクトで設置された簡易井戸の維持管理システム向上や普及で、飲料水用のロープポンプを補修や保全活動を村民の手で行えるよう実地研修を行いました。
また、民族紛争の激化により、首都に退避していた時期には「手洗いソング」を作成し、幼稚園や村の子供たちに手洗いの大切さを伝える活動を行いました。
エチオピアの主食であるインジュラは直接手を使って食べることから、需要に即した活動となり、
WASHステークスホルダー会議で紹介されたり、エチオピア水プロジェクトwash公式ソングに採用されました。
手洗いソングを中心としたこれらのプロジェクトはスーダン難民にも波及したそうです。
帰国後に発生したコロナウイルス感染症の世界的流行時には、国際NGOより感謝の意を示した連絡が届いたそうで、国際ボランティアのやりがいを感じた瞬間だったと仰っていました。
現在は上本町にある公益財団法人太平洋人材交流センター(PREX)に勤務している佐賀氏。
この仕事の目的は「人が育つことを通じて、誰もがもっと暮らしやすく、誰もが互いを尊重し合う社会を創ること。」
佐賀氏がPREXを就職先として選んだ理由には派遣前訓練所や派遣後のエチオピアで出会った同志たちとの繋がりがきっかけだったと言います。
PREXの主な活動は、途上国の地域や企業の成長と日本の企業の発展を結ぶための研修事業で、創立35年となる現在、研修参加者は158ヵ国から19,887名に上ります。
ここ数年は持続可能な開発目標を学ぶ上本町SDGs大学を中心とした日本人向けの研修も展開しています。
学生からは「エチオピアでの休暇の過ごし方について」「ホームシックにはなりませんでしたか?」「日本人の口に合う食べ物はありますか?」
「生肉を食べてお腹を壊しませんでしたか?」「言語の違いをどのように乗り越えましたか?」等の質問が寄せられました。
学生に貴重なお話をしていただき、誠にありがとうございました。