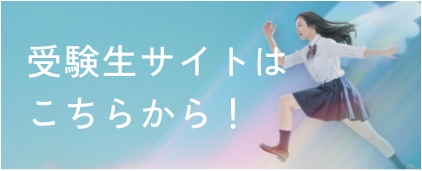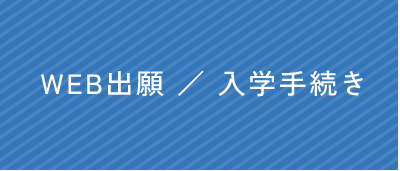図書館(学術情報・地域連携課)
科学研究費助成事業
科学研究費助成事業(科研費)
人文・社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる「学術研究」(研究者の自由な発想に基づく研究)を格段に発展させることを目的とする「競争的研究資金」であり、ピア・レビューによる審査を経て、独創的・先駆的な研究に対して文部科学省及び日本学術振興会が交付する助成金です。
科学研究費助成事業(科研費)関連規程・資料
科学研究費助成事業への応募に関する規程 公益通報者保護等に関する規程 「羽衣国際大学-不正防止・コンプライアンス推進体制図」 研究活動及び競争的研究資金等の使用に関する行動規範 羽衣国際大学公的研究費内部監査内規
採択実績
2023年度採択一覧
人間生活学部
氏名
山下 絵美
種目
若手研究
代表/分担
代表
決定金額(総額)
4,680,000
研究課題
形状に特徴のある大阪府特産野菜の調理法別科学的特性の解析および食教育への応用
実績の概要
近年、在来品種を伝統野菜として認証し、ブランド化の推進および消費拡大を図る取り組みが全国的に行われている。本研究の目的は大阪府が「なにわの伝統野菜」として認証されている19品目のうち、形状に特徴があり、一般家庭で用いられる可能性が高いと想定される品目(毛馬胡瓜、勝間南瓜、天王寺蕪等)について、調理法ごとの力学特性および嗜好特性を解明することである。そのため、伝統野菜と市販の一般品種を比較し、力学特性(物性測定、水分測定、咀嚼・嚥下筋電位測定)および嗜好特性(官能評価、成分分析)の解析を中心に行うとともに食教育への応用も検討する。
2022年度採択一覧
現代社会学部
氏名
田渕 宗孝
種目
基盤研究(C)
代表/分担
代表
決定金額(総額)
2,730,000
研究課題
北欧における民族主義と国民高等学校の関連性―福祉国家の形成基盤として―
実績の概要
本研究は、19世紀後半から20世紀前半の北欧における民族主義に着目し、それが1930年代における福祉国家成立に与えたインパクトを考察する。対象は特にデンマークを起源とする国民高等学校とし、同学校を通じて共有されていった民族共同体思想のパフォーマティブな影響力の考察を試みる。その際、隣国ドイツとの民族主義の言説的異同は重要なポイントとなる。類似するゲルマン民族主義が一方ではそれが福祉国家体制へ、もう片方はナチズムへと歴史的に連なっていったのであり、本研究では従来好意的に受容されてきた北欧の「民主主義」と民族主義との関係を明らかにし、北欧の独自の近代意識を新たな観点で提示することが狙いである。
人間生活学部
氏名
惠美 真子
種目
基盤研究(C)
代表/分担
代表
決定金額(総額)
3,380,000
研究課題
中学生男子選手における3年間のスポーツ栄養サポートの実践と将来予測分析の基盤構築
実績の概要
中学生男子は第二発育急進期(スパート)の最中にあり、アスリートであればさらにエネルギー消費量が大きく代謝に必須な栄養素が多種多様であるため、中学3年間継続したスポーツ栄養学的介入が要である。本研究では、応募者が継続的に栄養サポートしている地域サッカークラブの中学生選手と保護者の協力を得て、3年間の栄養サポートを実践し、継続的に身体組成や体力レベル・ケガの発生状況・血液性状・食事摂取状況等を調査してそのデータを蓄積する。さらに高校生以降の身長・体重・競技成績等のデータも取得し、スパート前の中学生に「こう食べれば将来こういう体格・選手になれる」可能性を示す「将来予測分析」を作成する基盤を構築する。
2021年度採択一覧
現代社会学部
氏名
岡崎 拓
種目
若手研究
代表/分担
代表
決定金額(総額)
2,600,000
研究課題
中欧における次世代自動車へのシフトとバッテリー生産集積に関する研究
実績の概要
本研究は、自動車産業の次世代自動車へのシフトが進行する状況での、中欧地域における自動車生産ネットワークの変容を分析するものである。1990年代以降、低賃金を主たる動機とした低付加価値小型車生産基地として量的成長を遂げた中欧地域が、次世代自動車シフトを契機とし高付加価値化を実現する可能性があるのか、加えて大手自動車メーカーの欧州自動車生産ネットワーク内の生産体制・サプライチェーンが変化しているか否かをバッテリー生産集積とR&D部門の拡大可能性に注目して分析を行う。GVC分析に基づく産業ネットワーク分析、政策面を含めたR&D動向の分析を行う。
氏名
吉村 宗隆
種目
基盤研究(B)
代表/分担
分担
決定金額(総額)
17,160,000
研究課題
学長リーダーシップのあり方に関する総合的研究
実績の概要
大学改革を進めるために、学長の役割はきわめて重要である。学長に権限を付与する形で改革が行われてきたが、大学経営者としての学長の能力を高めて、学内構成員やステークホルダーから支持される学長リーダーシップこそが必要である。 本研究では、学長はもちろんのこと、教員や理事・役員等の調査を通じて、望ましい学長リーダーシップ、学長の支援体制、学長選考・養成、学長への牽制のあり方など、学長リーダーシップについての総合的な研究を行う。理論と実践の往還を意識し、学術研究のみならず、学長研修などのアクションリサーチを併用する。
2019年度採択一覧
人間生活学部
氏名
渋谷 光美
種目
基盤研究(C)
代表/分担
代表
決定金額(総額)
4,290,000
研究課題
フィリピンにおける生活困難層の子どもへのケアサポートに関する研究
実績の概要
フィリピンにおける生活上の困難を抱える子どもへの教育と社会的ケアサポートに関する実情を把握し、問題解決への展望と課題を見出すことを目的としている。 フィリピンのデイケアセンター(保育所)、養護児童施設、高齢者と子どもとの混合型施設や、養護者のいない子ども達への教育とケア実践をしているNPO等、訪問実績のある子どもの事業所、施設、団体等を中心に再訪し、保育士やケアスタッフ、ケアラー等に対するインタビュー、アンケート調査を実施する。 また、先進諸国での子どもの教育とケアに関する文献研究や、国内の子ども・子育て支援に関するインタビュー調査も実施し、分析、検討する。その調査結果も踏まえ、社会発信する。
2018年度採択一覧
現代社会学部
氏名
内田 知巳
種目
基盤研究(C)
代表/分担
代表
決定金額(総額)
3,510,000
研究課題
360度全周囲カメラによる教育実践記録と「学習成果可視化システム」の構築
実績の概要
今年度も、昨年度に引き続き、新型コロナウィルス対策の影響を受け、久留米工業大学との共同研究である特別支援学校へのサービスラーニング実施に至らなかった。 現行に流通している映像解析ソフトでは、4K映像や360度映像を入力映像として扱えるソフトウェアがないため、映像編集ソフトを使用しているが、これまで研究に使用してきたGrassVallyEdiusでは、平方展開画面でしか再生・視聴することが出来なかった。昨年度より動画解析のための編集ソフトをEdiusからPremiereに変更し、360度映像を展開平面ではなく、HMDで任意の方向を視認しながらタギングを行う方法を試行中である。 学外での記録が難しく、学内の実習風景実施状況を記録し、授業評価に反映させる試みを始めた。 今期研究内容を学会などで発表できる形にまとめることが出来なかったので、次年度の課題としたい。
氏名
池田 玲子
種目
基盤研究(C)
代表/分担
代表
決定金額(総額)
3,120,000
研究課題
仕事と治療の両立支援のあり方‐がん治療の事例から‐
実績の概要
本研究の目的は、勤続・就労を希望するがん経験者に対して、企業による仕事と治療の両立支援の望ましいあり方の検討にある。仕事と治療の両立に関する文献調査とがん経験者へのインタビュー調査を実施した上で、職場状況とWCS(working cancer survivor)の存在を想定した対応についてアンケート調査を実施し、仕事と治療の両立に有効な職場の条件の一部を明らかにした。「良好なコミュニケーション」「WLBに配慮する雰囲気」に加えて、「お互いの仕事がカバーできるようになっていること」すなわち、職務設計等の職場のマネジメントが、罹患相談(=支援要請)の有無に影響することが明らかとなった。を学会などで発表できる形にまとめることが出来なかったので、次年度の課題としたい。
2017年度採択一覧
人間生活学部
氏名
中井 久美子
種目
基盤研究(C)
代表/分担
分担
決定金額(総額)
4,290,000
研究課題
過疎地住民のコミュニティ・エンパワメント強化のための教育支援システムの開発
実績の概要
我々は、過疎地域住民の自助や互助の意識向上を目的として、食生活や運動、認知症に関する教育プログラムを開発し,管理栄養士による減塩体験学習、理学療法士による身体活動能力測定と指導、認知症サポーター養成講座を事前申請者に提供しした。18~64歳までの住民を対象とした事前・教育後の調査比較では推定塩分摂取量は減少、委員会活動などの相互活動が増加し、エンパワーメント影響要因は、「信頼できる相談相手の存在」「他者との交流」「近隣との生活協力」であった。互助実践者インタビューから、活動を喜ばれることがモチベーション向上となり、これらの要因強化が、コミュニティエンパワーメント強化につながることが示唆された。
2016年度採択一覧
人間生活学部
氏名
稲垣 秀一郎
種目
若手研究(B)
代表/分担
代表
決定金額(総額)
3,770,000
研究課題
発酵食品の機能性に寄与するアミノ酸代謝物の網羅的解析と機能性食品開発への応用
実績の概要
近年,米の消費量の低下が顕著となり,米の用途拡大が求められている。本研究では,新規米発酵食材の開発を目指し,アジアのさまざまな糖化微生物を用いて調製した米発酵物の成分分析および機能性調査を行った。成分分析においては,糖化微生物種の近縁性によって糖化能やアミノ酸生成能に相関が見られるかに着目したが,一定の傾向はあるものの例外も存在していることから,一概に法則性があるという結論には至らなかった。機能性評価の一つとして測定したDPPHラジカル活性では,試験した13種の微生物の酢酸エチル抽出物のなかでAspergillus awamoriに最も強い活性が見出された。
氏名
片山 千佳
種目
基盤研究(C)
代表/分担
分担
決定金額(総額)
4,420,000
研究課題
介護人材の離職ストップのための支援ツールの開発-ストレスマネジメントの観点から-
実績の概要
2016年には697名を対象にアンケート調査を実施した。(有効回収率79.1%・有効回答率97.5%)「共感疲労・レジリエンス因子となる要因」について、ライカート式5段階評価尺度法を用いて回答を得た。因子分析の結果、各5項目が抽出できた。支援者の離職を防止し、質の高い支援を利用者に還元することを目指す「支援者支援(職務ストレス・レジリエンスセルフチェック)ツール」を2018年に作成した。2017年には600名の調査協力を得てツールの有効性を検証し偏差値換算表を作成した。ツールの作成経過と詳細な内容および具体的な活用方法については、天理大学リポジトリにて公開している。
氏名
中川 ゆかり
種目
基盤研究(C)
代表/分担
分担
決定金額(総額)
3,640,000
研究課題
敦煌書儀による書記言語生活解明のための基礎的研究
実績の概要
敦煌書儀伯三四四二の「吉凶書儀」について、翻刻、加点、語釈、意訳など注釈作業ができた。さらに、敦煌書儀の語彙や表現について、日本古代の文献資料との比較検討も行った。その検討の過程で得られた新たな知見については、補注という形で纏めている。補注には、書簡用語や書簡の文化的背景に関する新たな知見も盛り込むことができた。
氏名
辻本 洋子
種目
基盤研究(C)
代表/分担
分担
決定金額(総額)
4,420,000
研究課題
乳幼児健診を利用した母親の食生活と低出生体重児の出現の要因の検討
実績の概要
3地区で、3または4か月健診を受診した親子に対し質問紙調査を実施し、その後、1歳6または9か月児健診までコホート調査を行った。低出生体重児の母親の群では、妊娠前と妊娠中の乳製品摂取が低かった。また、妊娠期の推奨体重増加量区分別の分析により、体重増加量不足・過剰群は適正群に比し食知識が低いなど、食に関連した因子の抽出がなされた。1歳6または9か月児健診の調査では、朝食を毎日摂取する母親の子どもは、良好な食生活であることが示唆された。
2015年度採択一覧
現代社会学部
氏名
小田 まり子
種目
基盤研究(C)
代表/分担
分担
決定金額(総額)
2,600,000
研究課題
知的障害を持つ肢体不自由児のための入力機器の開発
実績の概要
肢体不自由児のための以下の入力装置の開発を行った。(1)薄型のタッチセンサモジュール。USBキーボートとして扱える入力装置だが、これまでタッチセンサ部分が厚く(約1㎝)、利用者が限定されていた。これを部品を改良して3mm未満にまで薄くすることができた。 (2)関節の曲がりを検出する入力装置の小型化と無線化。特定の関節のみの自由が利く児童に装着して使用する入力装置だが、センサ信号の処理のため小型の計算機を取り付けており、大きく重くなって利用者を限定していた。これを電池駆動できる無線モジュールを付けて計算機と分離することにより、小型化と無線化を実現し、利用者の幅を広げた。
氏名
小田 まり子
種目
基盤研究(C)
代表/分担
代表
決定金額(総額)
4,810,000
研究課題
大学連携サービスラーニングによる地域特別支援学校のための工学的・教育的支援
実績の概要
本研究では、情報通信技術を生かした大学生のサービスラーニングにより特別支援学校への技術的・教育的支援を行った。知的障がい児が興味を持つ3D-CGアニメーション、音声、拡張現実技術を用いて、積木学習、文字やシンボルの学習、ボウリングによる算数学習など学習者に合わせた多種類の学習教材ソフトを開発した。また、障概要を持つ児童生徒の多様なニーズに合わせた入力機器も開発した。本学習用教材や入力機器を用いた特別支援学校での教育支援の結果、学習効果が確認できた。工学系大学生にとってはユーザインターフェイスを考えたソフトウエア開発、障がい児を支援する貴重な教育経験となり、技術力と社会性の向上につながった。
2014年度採択一覧
現代社会学部
氏名
泉 紀子
種目
基盤研究(C)
代表/分担
分担
決定金額(総額)
4,810,000
研究課題
伊勢物語絵の体系構築に向けた近世作品の研究ー住吉如慶筆「伊勢物語絵巻」を中心にー
実績の概要
住吉如慶筆「伊勢物語絵巻」(東京国立博物館蔵)に描かれた80章段の各絵画場面について物語の内容がどのように絵画化されているのか読み取りを行った。美術史、国文学、建築史・住宅史の3分野の研究者が、住吉如慶の作風や絵画表現について、注釈書や版本の図様との比較をとおして、討議を重ね検討した。その結果として、本絵巻は伊勢物語絵の伝統をふまえて、独自性を備えた場面解釈や絵画表現を持つ作品であることが明らかになった。この研究によって、伊勢物語絵の体系を構築する上で、江戸時代前期を代表する作品として基礎的な研究データを得ることができた。この研究成果を研究書として公刊する予定である。
人間生活学部
氏名
宮﨑 陽子
種目
若手研究(B)
代表/分担
代表
決定金額(総額)
3,380,000
研究課題
高等学校家庭科における住宅事情・住宅問題・住宅政策学習の研究
実績の概要
本研究は、高等学校家庭科での「住宅事情・住宅問題・住宅政策」学習(居住改善学習)の指導実態と意識を質問紙調査等によって明らかにし、この分野の学習を充実させるために必要な課題について考察することを目的とした。主な結果は以下の通りである。 1)家庭基礎による授業時間数不足と内容精選が、住生活領域と居住改善学習の機会と内容の縮減を一層促している。2)居住改善学習は指導上の様々な問題を抱える分野だが、教員の多くがその必要性を認識している。3)居住改善学習の教材開発と授業実践を試行的に実施した結果、他分野との連携した授業展開の可能性などが見いだせた。
氏名
中川 ゆかり
種目
基盤研究(C)
代表/分担
代表
決定金額(総額)
4,550,000
研究課題
正倉院文書の読解を通した上代文学の表現の生成に関する研究
実績の概要
奈良時代の下級官人達が書き表した膨大な文書の集積である正倉院文書を読み解くことによって、当時の官人達の書く文章の実態・人間関係のあり方・信仰の様相を明らかにした。又、『古事記』や『日本書紀』・『風土記』には見えない言葉を発掘し、上代語の知見を広める事が出来た。さらに、正倉院文書の文章とそれらを比較することによって、それぞれの作品の文章の性格を浮き彫りにし得た。
2013年度採択一覧
現代社会学部
氏名
森岡 ゆかり
種目
奨励研究
代表/分担
代表
決定金額(総額)
600,000
研究課題
近代女性漢詩人白川琴水著『本朝彤史列女伝』についての基礎的研究
実績の概要
本研究は、『本朝彤史列女伝』について、1書誌学的調査、2作品論的研究、3伝記的研究を行うと共に、書籍とその作者の顕彰と普及を行なうことをめざした。 天理大学図書館本などの閲覧や文献複写を行い、白川琴水の生家である願生寺(岐阜県高山市)で史料調査を進めた。願生寺には三種のテクスト(甲本、乙本、丙本)が存在し、他の機関の所蔵本との校比によって、願生寺の乙本を定本として断じるに至った。なお、校比の結果、願生寺甲本が特異な本文を有することが判った。 甲本は、現在風に言えば、初校に当たり、誤字や不十分な説明表現を含んでいる。しかし、そのために却って、例話の多くが『大日本史』列女伝を原拠とするという作品論として重大な点が明らかになった。そしてそれは伝記的疑義についての核心に迫る糸口ともなった。 調査研究の成果は、第33回和漢比較文学会大会(2013年9月29日)で「白川琴水著『本朝彤史列女伝』について――『大日本史』列女伝との比較を中心に――」と題して発表し、研究発表要旨が『和漢比較文学』第52号に掲載された。さらに、顕彰と普及の活動として講演活動を2度行なった。まず、2013年10月20日、願生寺にて、「幕末明治の高山にスゴイ”歴女”がいた! ――『本朝彫史列女伝』を著した才媛白川琴水――」と題して講演を行なった。これは『高山市民時報』「街角掲示板」(2013年10月14日)で紹介された。次に、2014年2月8日、佐保会大阪支部にて、「文豪だって漢詩をよんだ――女性たちの場合」と題して講演を行なった。なお、『本朝彤史列女伝』に関するホームページを設けて研究成果の普及に資した。加えて、本研究の成果は、「白川琴水『本朝形史列女伝』についての初歩的考察――願生寺所蔵本を手がかりとして」と題して、飛騨学の会の研究紀要『斐太紀』通巻11号に掲載される。
人間生活学部
氏名
稲垣 秀一郎
種目
若手研究(B)
代表/分担
代表
決定金額(総額)
4,030,000
研究課題
アミン化合物に着目した,発酵による機能性向上機構の解明と新規米発酵食材の開発
実績の概要
アジアの発酵食品から分離されているさまざまな微生物を用いて米発酵物を製造し,その成分分析および生理活性を評価した。いずれの発酵物においても未発酵物と比較してポリフェノール,アミノ酸含量,還元糖量などの含有量が増加しており,微生物による活発な代謝活性が生じていることが示された。特に2種のRhizopusを用いた発酵物では高値を示した。生理活性評価では,抗酸化活性および脂肪分解活性が発酵によって有意に上昇することを明らかにし,特にMucor cillcinellodesを用いた発酵物において顕著であり,これらの生理活性を有する新規米発酵食材を開発するためのスターターとして有望であることが示された。
氏名
渋谷 光美
種目
基盤研究(C)
代表/分担
代表
決定金額(総額)
5,200,000
研究課題
EPAに関連するアジアでの介護人材養成の動向
実績の概要
フィリピンのケアギバーの資格は、国内外でのケア人材として、高齢者、特別なニーズを有する人だけではなく、子どもへのケア対応が目指されたカリキュラムである点に着目した。多様な対象者へのケア教育である理由は、個人宅でのケア人材として、外国での労働が想定されているからである。 国内では、経済格差の拡大による貧困問題や、今後高齢化の進行が予測されるにもかかわらず医療・保健制度やサービスの未整備等が問題視されている。ケア人材を必要とする民間の施設や事業所等も増加してきている。今後は、子どもの教育とケアを必要とするデイケアセンターでのケア人材としての可能性についても検討していくべきではないかと考えられた。
氏名
塚元 葉子
種目
基盤研究(C)
代表/分担
代表
決定金額(総額)
5,070,000
研究課題
インビボホールセル記録による無麻酔ラット皮質ニューロン膜電位と脳波との連関の解析
実績の概要
脳波とは大脳皮質に発生するリズム性電位変化の集合であり、樹状突起に起こるシナプス後電位の集積であると教科書的には言われている。従来の研究では、技術的な問題から麻酔下の動物の記録しか安定せず、覚醒動物の様々な脳波とアラーム膜電位変化との比較は困難であった。麻酔覚醒ラットの前肢押しレバー運動中の脳波と眼圧電位を同時に誘導し、両者の連関を解析することを試みた。の脳波と視線膜電位の間は高い相関があり、それが行動の多少によって変動することが分かった。
2012年度採択一覧
現代社会学部
氏名
小田 まり子
種目
基盤研究(C)
代表/分担
代表
決定金額(総額)
3,120,000
研究課題
知的障害児のための3Dを用いた文字発音学習支援システムの開発
実績の概要
知的障害児のための3次元CGアニメーションを用いた教育支援ソフトウエアを開発した。平仮名文字学習CGアニメーションを用いて、知的障害を持つ児童は平仮名の形状を認識し、発音と平仮名の関係を学ぶことができる。また、口唇動作CGアニメーションを見ながら発音練習が可能であり、文字、発音、口唇動作を組み合わせて学習できる。児童の理解度、定着度を確認しながら学習が進められるように、ドリル型やゲーム型の平仮名学習教材ソフトウエアも開発した。 久留米支援学校において本ソフトウエアを利用した授業を定期的に実施し、大学生が教育支援を行った。学習過程における平仮名読みの正解率を調べた結果、有意に向上していた。
人間生活学部
氏名
池 晶子
種目
基盤研究(C)
代表/分担
代表
決定金額(総額)
4,160,000
研究課題
ミネラルバランスと水構造の解析に基づいたおいしい水指標の提案
実績の概要
水道水に含まれるミネラル成分の種類やバランスがどのように味に貢献しているかを分析した。国内14地域で供給される水道水を対象に、「順位法」と「基準比較法」の2種類の官能試験を行い、ICP-MSで分析した微量ミネラル成分濃度との相関を遺伝的アルゴリズム解析と部分最小二乗法にて解析した結果、元素Li、Fe、Cu、Mo、Pbの味への関与が示唆された。また、主成分解析でも同様の結果が得られた。FeとLi濃度と、味の評価値の関係をクロス集計にて調べたところ、高濃度のFeに低評価を示し、高濃度のLiに高評価を示す割合が多いことが明らかとなった。
2010年度採択一覧
人間生活学部
氏名
田中 雅子
種目
基盤研究(C)
代表/分担
代表
決定金額(総額)
3,120,000
研究課題
企業組織全体における理念浸透のプロセスと施策
実績の概要
本研究は、一企業の経営者、中間管理者、一般従業員といった各層へのインタビュー調査を、複数企業に対し実施するなかで、経営理念の浸透を「内面化」と「定着化」という双方の視点から検討した。特筆すべき結果は、「内面化」においては、転機となる経験が敷石となり理念の理解を深化させ、それが部下対応にも影響を与えることを、「定着化」においては、理念の内容表現が浸透プロセスに影響を与えるため、それに応じた浸透施策をとることが有効であることを挙げることができる。
氏名
中川 ゆかり
種目
基盤研究(C)
代表/分担
分担
決定金額(総額)
3,900,000
研究課題
正倉院文書による日本語表記成立過程の解明
実績の概要
正倉院文書を古代の実用世界の国語資料と位置づけ、外国語の文字である漢字漢文を用いて、如何に日本語を表記したのかということを具体的に解明した。文書作成に携わる下級官人たちは、任務を遂行するために、言葉によって銭や人や物を動かさなければならない。その過程で生まれたのが、和製漢語や漢語に対する新しい意義の付加、日本語特有の助字の語法であった。
2009年度採択一覧
人間生活学部
氏名
三上 和夫
種目
基盤研究(C)
代表/分担
代表
決定金額(総額)
3,120,000
研究課題
地域学校の制度構成-発展的経路の多元モデル-
実績の概要
本研究は、学区論と経済理論とを総合的に把握することを目的としたものであり、一般行政団体によって実施されてきた学事、とくに学校施設を中心とする教育関連施設の設置運営の動向と、それら施設と関係する地域的有志的組織の歴史的生成と価値意識の構成を検討した。具体的には、「地域学校の資本形成の歴史検証」と「教育の意思決定と資源体系」の検討を行うことで、制度の内部構成、制度の複合的編成、施設運営費用の社会的承認の作法の三つの相互関係から、制度運用に際しての公平性の確保とリスク軽減の方途を探ることを目指した。 第一に、研究目標の一つである「地域学校の資本形成の歴史検証」は、研究分担者である湯田が行った。その結果、対象である神戸市では、商業系教育機関への進学者の増大も進行した。そして、その進学者が、高等商業教育機関に連なる商業系教育機関を安定的に支持する基盤となり、戦後の商業系の中等教育機関や高等教育機関の拡大に連なることを指摘した。このことは、ミクロな社会過程による教育機関の発展が、商業系教育でも営まれていたことを示したものである。 第二に、もう一つの研究目標である「教育の意思決定と資源体系」では、研究代表者である三上と末冨が行った。末冨は、教育資源の中でも政府の負担する公教育費と家計の負担する私教育費との流れに焦点をあてた分析を担当した。具体的には、戦後の公私負担の変動過程から、「公私混合型教育費負担構造」の特徴と課題を把握したうえで、今後の教育費の公私関係を「公私分担型教育費負担構造」へと移行させる必要性とそのための教育財政に求められる機能や条件について検討を行った。 研究代表者の三上は、近年刊行された関連学術書を整理し、先行研究の検討と総括的な課題設定を試みた。そして、物理圏・生命圏・人間圏の合成としての空間-世界像を前提に、両次元の複合・模式的構成と相互交流を行うことで、社会と学習者世界の内的構成が進行することを指摘した。さらに、内的構成が進行するに際して、社会活動の局面での価値争奪性も発生するが、人格内部の統御が社会生活圏にも連なることで、公平性を確保し、リスクを制御して発展の契機になる可能性を示した。
氏名
池 晶子
種目
基盤研究(C)
代表/分担
代表
決定金額(総額)
4,420,000
研究課題
ミネラルバランスと水構造の解析に基づいたおいしい水指標の提案
実績の概要
水道水に含まれるミネラル成分の種類やバランスがどのように味に貢献しているかを分析した。国内14地域で供給される水道水を対象に、「順位法」と「基準比較法」の2種類の官能試験を行い、ICP-MSで分析した微量ミネラル成分濃度との相関を遺伝的アルゴリズム解析と部分最小二乗法にて解析した結果、元素Li、Fe、Cu、Mo、Pbの味への関与が示唆された。また、主成分解析でも同様の結果が得られた。FeとLi濃度と、味の評価値の関係をクロス集計にて調べたところ、高濃度のFeに低評価を示し、高濃度のLiに高評価を示す割合が多いことが明らかとなった。
2008年度採択一覧
人間生活学部
氏名
中田 和江
種目
若手研究(B)
代表/分担
代表
決定金額(総額)
4,420,000
研究課題
腸管マクロファージのCD14発現制御機構に関する研究
実績の概要
腸管マクロファージのLPS低応答メカニズムについて、CD14(LPS受容体)の発現制御機構に着目し解析を行った。本研究の結果、腸管マクロファージのCD14はコントロール細胞よりも高分子であること、また糖鎖修飾を受けていないことが示唆された。今回明らかになった結果は、組織マクロファージの異物に対する過剰応答を抑制する制御機構として、CD14の翻訳後修飾における新規な制御機構の存在を示唆していると考えられた。
2007年度採択一覧
人間生活学部
氏名
新井 康友
種目
若手研究(B)
代表/分担
代表
決定金額(総額)
1,480,000
研究課題
介護保険制度施行後におけるホームヘルパーの労働と健康に関する研究
実績の概要
A県とB県のホームヘルパーを対象にアンケート調査とインタビュー調査を行った。その結果、それぞれのホームヘルパーが希望する雇用形態に採用されていない場合、介護福祉士の資格取得などを切っ掛けに転職する者もいることがわかった。そのため、それぞれのホームヘルパーがもっている働く目的に応じた雇用形態で採用することが働き続けることになることがわかった。しかし、現在の介護報酬では多くの常勤ヘルパーを採用できる条件ではなく、各事業所での努力にも限界がある。また、雇用形態が安定すればするほど、健康状態の不調を訴える者が多いこともわかった。
氏名
後藤 由美子
種目
基盤研究(C)
代表/分担
分担
決定金額(総額)
2,730,000
研究課題
外国人介護士の教育研修プログラムの開発
実績の概要
研究成果の概要:フィリピン人介護・学生看護やインドネシア人介護福祉士の調査から、外国人介護士はEPAにおける日本での就労に対して高いケア技術の習得を期待し、日本語人間や関係を心配していることが分かった。在日フィリピン人介護士の調査からは、日本語の記録や日本人介護士との関係が困難であることが判明した。日本人介護士と協働するための教育研修プログラムとして、介護現場における異文化コミュニケーションの教育が重要であることが分かった。
氏名
中川 ゆかり
種目
基盤研究(C)
代表/分担
分担
決定金額(総額)
3,250,000
研究課題
正倉院文書訓読による古代言語生活の解明
実績の概要
正倉院文書の訓読と注釈という基礎研究を通して、古代日本語の実用世界における言語生活の解明を行った。原本の観察に基づいて、文字の形と語の関係・言葉と事柄との関連を検証し、8世紀の役人たちが、どのような言葉や表現を生み出していったのかということを具体的に示した。このことによって、これまで国語資料として評価されなかった正倉院文書を、古代の生きた言語生活を解明する国語資料として位置づけることができた。
氏名
木脇 奈智子
種目
基盤研究(C)
代表/分担
分担
決定金額(総額)
4,550,000
研究課題
多様なひとり親家族の韓日比較-未婚・非婚・既婚の親子のジェンダー分析-
実績の概要
日本と韓国では、少子化が解消されない中で、ひとり親家族が増加している。未婚、離別、死別など様々な状況にあるひとり親家族の多くは経済的な問題とともに社会的偏見による問題を抱えている。そこでこの調査は、特にひとり親家族に対する社会的イメージに焦点を当て、これから家族を形成する大学生を対象として調査を行った。日本での調査は、2007年7月に九州、近畿、東海、東京の各大学に所属する大学生を対象として行った。配布数1796、回収数1379、回収率76.8%であった。大学生の家族イメージに,世間のひとり親の否定的イメージが大きな影響を与えていた。そして家族の授業をうけていない学生もひとり親に対して否定的イメージを持っていた。韓国では大学生を対象に2007年10月から11月の間に,2000部の調査票を配布し,1605人から有効回答を得た.有効回答率は80.3%である.分析の結果は以下のとおりである.第1の将来のライフコースについては,大学生の8割に近い人が,就職,結婚,出産の順によるライフコースを経験することを望んでいた.第2のひとり親の子育てに関する大学生の意識は,未婚,離婚,死別の背景により異なった.大学生が最も否定していたのは,未婚の親の子育てで,最も理解していたのは,死別によるひとり親の子育てである.第3の大学生がひとり親の子育てに対して肯定的な意見を持つのに最も影響を与えた要因は,ひとり親の子育てに対する世間のイメージであることから,社会で形成されている価値観に多く影響を受けていることが明らかになった.
2006年度採択一覧
現代社会学部
氏名
中川 恵
種目
基盤研究(C)
代表/分担
代表
決定金額(総額)
2,400,000
研究課題
女性・メディア・世論形成-中東地域6カ国のフィールド調査を通して-
実績の概要
大衆への普及が過去10年以内という点で新しいメディアと位置づけられるインターネットと衛星放送の普及が、中東地域の生活空間、政治的意思の形成、政治的意思形成の場となる公共空間にいかなる変容をもたらしているのか、とりわけ女性たちの政治的意思決定のプロセスを調査・分析した。その結果、モロッコの場合、衛星放送の普及と国家が進める社会・経済開発の両方がほぼ同時に進んだことが、女性の政治参加を促進したと結論づけることができた。
人間生活学部
氏名
岸本 幸臣
種目
基盤研究(C)
代表/分担
代表
決定金額(総額)
3,490,000
研究課題
近年の「住み方変化」に対応した新たな住宅平面の提案に関する研究
実績の概要
本研究は前年度に引き続き、住宅の平面構成と実際の住み方におけるLDK空間利用の「乖離」(ずれ)の実態とその矛盾の背景を明らかにし、新たな住宅の平面構成理論の課題を整理する事を目的としている。前年度(平成18年度)の考察では、「改善型乖離」と「矛盾型乖離」の存在を指摘し、これが家族員数・団らん室面積・団らん室の持ち込み行為等に影響されていることを明らかにした。特に、これが団らん行為と接客行為の空間的処理に大きく影響していることを指摘した。平成19年度は、この成果を踏まえて2つの実態調査を実施した。第1次調査では、具体的な住み方実態の平面採種調査と居住者の意識調査を実施し、175票の有効回収票を得た。その結果、住み方実態における独立接客室の確立度は低く、住み方実態としての接客行為は多様な空間利用がなされていた。しかし、接客意識としては格式的来客の団らん室対応を回避しようとする傾向の強いことと、それが乖離誘発の主な要因にもなっていることを把握出来た。第2次時調査では、団らん機能と格式的接客機能とを両立させる空間についての提言を試み、居住者の評価をアンケート方式で調査し、232票の有効回収票を得た。実際の住み方での接客対応では、気の張る客を団らん室でもてなす事への強い抵抗感が認められた。この結果、接客行為を家族の団らん空間や私的空間から分離しようとする要求の高く、この現象が、LDKプランタイプにおける乖離現象に大きく影響していることが確認できた。ただ、試行的に提案した「団らん・接客両立型L空間」の肯定的評価は4割止まりで独立接客室確保の志向が強く、公私の心的隔離度が更に高い多機能型団らん空間確立の必要性が確認出来た。尚、両調査結果は「第30回日本家政学会関西支部研究発表会」(2008.10)と、「第61回日本家政学会大会」(2009.5)に発表を予定している。
氏名
後藤 由美子
種目
基盤研究(B)
代表/分担
分担
決定金額(総額)
14,250,000
研究課題
重度認知症高齢者の感情反応と行動を手がかりにした基本的生活支援技術の開発
実績の概要
研究目的は、重度認知症高齢者の基本的な生活支援技術を明らかにして、その研修プログラムを開発し、重度認知症高齢者のQOLの向上を図ることであり、目的達成のために重度認知症高齢者を対象とした2カ月間の小集団回想法、6カ月間の手織りプログラム、5週間の生活支援技術に関する介入、及び国内外の看護職等への面接調査を通じて重度認知症高齢者への日常生活支援技術研修プログラムを作成し、複数回の研修を実施しそのプログラムが有効であることを評価した。
2005年度採択一覧
現代社会学部
氏名
田中 雅子
種目
萌芽研究
代表/分担
分担
決定金額(総額)
3,300,000
研究課題
経営理念とマネジメントプロセスと企業パフォーマンスの因果関係モデルの研究-
実績の概要
経営理念と企業パフォーマンスとの関係を考える上で、経営理念とその浸透・実践・実現プロセス(マネジメントプロセス)の相互作用に踏み込み、「経営理念・マネジメントプロセス・企業パフォーマンスを統合した因果関係モデル」を構築していくため、本研究では以下のような研究目的を掲げた。 [1]経営理念のグループ分類とそのキーワード・該当企業の同定(経営理念の言説への数理的分析)。 [2]マネジメントプロセスの測定指標及びグループ分類の同定(実務家向けアンケートの設計・分析)。 [3]「経営理念とマネジメントプロセスの相互作用が企業パフォーマンスに影響を与える因果関係モデル」の解明(企業理念キーワード・アンケートデータ・財務データの総合分析) 平成18年度にマネジメントプロセスの構成要素の体系化と測定指標の同定を行い、それらについて約250社の調査データを収集した。今年度は、該当する企業の経営理念のテキストデータを最新のものに更新し、それらを活用して以下の研究を進捗させた。 上記[1]については、収集・検分した企業の経営理念のテキストデータを、最先端のテキストマイニング技術を活用して分析し、経営理念のグループ分類とそのキーワード及び該当する具体的企業の同定を行なった。 上記[2]については、マネジメントプロセスについての調査データを説明変数とし、また財務データや測定指標のうちのモチベーション指標を被説明とした分析を行う。分析手法としては、共分散構造分析などの線形的な解析と、非線形解析の双方を実施し、理論構築におけるそれぞれのメリットとデメリットを実データに基づいて明らかにした。 上記[3]については、前年度に検討した上記[1][2]のデータを統合する分析枠組みにより、「経営理念とマネジメントプロセスの相互作用が企業パフォーマンスに影響を与える因果関係モデル」の解明を行なった。
2004年度採択一覧
現代社会学部
氏名
棚山 研
種目
基盤研究(C)
代表/分担
分担
決定金額(総額)
3,200,000
研究課題
都市の変容と都市型サービス産業の課題-消費・生活文化の視点もふまえて-
実績の概要
調査に基づく共同研究の結果、研究論点として、ドイツの各都市でNPO法人によって推進されている都市マーケティング(Stadtmarketing)の重要性を析出した。また都市マーケティングは、都市型サービス産業が直面している課題の解決の一視点でもあると結論づけた。この点を具体的に明らかにするために2005年2月および9月に、マンハイム及びケルンの都市マーケティングNPO及び商工会議所、市役所(スポーツ局、文化局)、地域スポーツNPO等関連団体へのインタビューと資料収集を実施した。 都市マーケティングのより深い究明については、今後も継続して研究する課題である。 各メンバーによる研究としては、(1)齋藤雅通は、ドイツにおける都市型の小売商業集積であるパサージュの実態調査に基づいて理論的可能性と限界を明らかにした。(2)土居靖範は、ドイツのケルンおよびカールスルーエの都市交通経営体や運輸連合の調査を行い、財源調達のしくみを主に解明した。またLRTの国内への導入を、具体的にJR富山港線のLRT化の経緯と課題を調査研究した。(3)近藤宏一は、主にドイツにおける都市公共サービス、とりわけ文化・芸術関連サービス(オーケストラ、歌劇場、美術館)と観光および公共交通にかかわる組織の現状と課題について調査と資料収集を行った。(4)棚山研は、サッカーの日韓W杯開催時から開催地である新潟の継続調査と調査データの整理を行った。併せて、2度にわたるドイツのスポーツクラブの調査を通じて、日独のスポーツクラブの運営、生活文化への定着度についての比較を試みた。(5)池田伸は、現代都市における消費者研究およびそれに係わる調査方法論について、社会統計学や文化人類学などの周辺領域の成果を含めて検討した。その結果,現代都市のポストモダニティをマーケティング(消費者行動)の社会学として構想するにいたった。(6)谷口知弘は、京都市出町地域の取り組みの現地調査に基づいて、市民参加のまちづくりについて論究した。
氏名
木村 純子
種目
基盤研究(C)
代表/分担
代表
決定金額(総額)
3,400,000
研究課題
消費文化のグローバル化・ローカル化・およびハイブリッド化に関する研究
実績の概要
【平成16年度の成果】 研究の経過過程で明らかにしたのは次の点である。日本で活発に行われている西洋文化としてのクリスマス消費を取り上げ、調査を行った。具体的には、消費文化の受容に関する(1)既存の分析枠組みを批判的に検討し、(2)新たな枠組みを提示し、(3)本研究が提示する枠組みを経験的に検証した。そこで明らかにしたのは、既存理論の限界である。これまでの議論は、西洋文化に日本文化を従属させる(グローバル論者)、あるいは日本文化に西洋文化を従属させる(伝統論者)といった「西洋中心の文化帝国主義モデル」であり、いずれも、文化を本質的なものとしてとらえ、日本の文化状況を均質化に行き着くものとして理解していた。ところが、調査を進めると、実際は、文化は西洋か日本かのいずれかに均質化していくわけではないことが明らかになった。われわれは、消費文化の変容とは、異文化を主体的に受け止め利用していく過程(=文化の再生産)ととらえるべきであることを主張した。 【平成17年度の成果】 平成17年度は第二次世界大戦後から現在に至るまでに(WHEN)、観光地という場において(WHERE)、それぞれどのような欲望を持って、どのように観光文化を構築し維持しているのかを(WHAT & HOW)、ローカルの人々・観光客・マーケターという異なる主体が(WHO)、主体間の相互作用に注目しながら明らかにする、という全体構想を持って行った。このような研究の全体構想の中で、以下の成果を出した。第一に、既存の文化認識論とは異なる新しい文化認識論を用いることの意義を明らかにした。第二に、第一で提示した枠組みを用いて経験的分析を行った。異文化に接するローカルな文化は、異文化をしたたかに利用しながら、文化の真正性とローカル・アイデンティティを構築していることを明らかにした。
人間生活学部
氏名
木脇 奈智子
種目
基盤研究(C)
代表/分担
代表
決定金額(総額)
3,700,000
研究課題
育児におけるジェンダー関係とネットワークに関する実証的研究:質的研究編
実績の概要
私たちの研究グループは、本調査に先立って、平成13年度・平成14年度にも、文部科学省科学研究費補助金(基盤研究(C)(1))を受け「育児におけるジェンダー関係とネットワークに関する実証研究」と題した大量アンケート調査を実施した。平成13年度調査では、マクロで見た場合の現代日本家族の子育ての特徴を明らかにした。その後私たちは大量調査ではすくいあげることができなかった個々の親たちの本音に迫りたいと考えた。また、平成13年度調査では分析の対象にできなかった単親家族、共働き家族、再婚家族、父親が育児休業を取得した家族など、近代家族を超える家族の子育てについても、取り上げ分析したいと思った。このような問題意識から実施したのが本調査である。 平成16年5月に本調査に着手し、初年度には研究会を重ねて先行研究の検討と質問項目を作成した。平成17年3月から平成18年3月まではインタビュー調査と分析を行った。 その結果母親22名、父親10名、計32名に生育歴や育児観、家事育児分担、ジェンダー観などそれぞれ1時間半におよぶインタビュー結果を得ることができた。対象者は当初平成13年度調査において「インタビュー調査に協力してもよい」と答えて下さった方々としたが、対象者の多様性を持たせるために、知人の紹介で関西圏に居住する共働きのご夫婦や単親家庭、再婚家庭へ対象者を拡げ、その結果を報告書冊子にまとめた。 報告書は6章からなり、1章「調査の目的と方法」、2章「男性の子育てと仕事との葛藤」3章「専業主婦の子育て分業意識・子育て観」4章「家事・育児の外部化」、5章「定位家族体験と親子関係」6章「男性にとっての家事・育児とはなにか」となっている。 夫婦で(別々に)インタビューを行っているカップルが多く、子育てや家事に関する男女の意識の違いやズレが明らかになった。
氏名
木脇 奈智子
種目
基盤研究(B)
代表/分担
分担
決定金額(総額)
7,100,000
研究課題
若年属におけるケア意識の実態とその形成過程に関するジェンダー論的研究
実績の概要
本研究は、若者のケア意識ケア倫理、ケア経験の実態を実証する調査研究によって明らかにし、ジェンダーの展望からケア意識の形成への影響を与える社会的・文化的事項を分析することを主な目的とするとする。3ヶ年数本研究では、第一にフェミニズム視点によるケア研究の理論的解釈を整理し、ジェンダー視点に続いて若者のケア意識研究の分析軸を検討した。その上で、ケアワーカー男女への聞き取り調査(ミクロ分析)、若年層男女を対象とした質問紙調査(統計的分析)を実施し、それらの統合的検討を通して、ジェンダー平等なケアワークの実現に向けた課題を明らかにした。組織者全員の協力体制のもと、研究計画に沿って研究の理論的・実証的深化を図った。研究成果は報告書としてまとめたほか、4件の学会報告(国際ジェンダー学会、日本社会学会 1. 聞き取り調査のと分析 聞き取り調査(平成16-17年度) )では、男性介護職を中心に、介護、看護、保育に携わる若年層男女を対象に詳細なインタビューを実施し、職業キャリアの形成過程、家族関係、ジェンダー意識など多岐にわたる内容を分析した。仕事をやる気にする契機として子ども時代のケア経験、家族(親、祖父母)の影響が明らかになったほか、ジェンダー化されたケア労働の実情、男性の参入によるジェンダー構造の流動可能性について示唆を得る2. 質問紙調査の実施と分析 聞き取り調査の知見をふまえ、平成17年度には質問紙調査「若者のケア意識調査」(回収数1171票)を実施し、若年層男女のケア意識全般を把握し、ケア分野(介護、看護、福祉)で学ぶ学生と、一般学生の比較分析を行った。ケアワーク学生志向の職業観、キャリア形成過程への家族への影響、男性がケア職に就く際の困難な認識度など、多様な知見が得られた。
2002年度採択一覧
現代社会学部
氏名
酒井 治郎
種目
基盤研究(C)
代表/分担
代表
決定金額(総額)
1,000,000
研究課題
営利企業と非営利組織体の会計的枠組み統合化の研究〜FASB概念書を通しての検討〜
実績の概要
本研究は、近年、わが国で問題となっているNPO(非営利組織)と、それに伴う会計問題を対象に検討を行ってきた。これまでNPOに係る事件の背景には、NPO会計の不備がその原因の一つとなっていると考えられる。そこで、本研究はNPOの会計問題を解決し、これからのNPOの発展にも寄与することを意図している。 まず、統一化の可能性を、アメリカの会計学者であるWiliiam.J.Vatterが提唱した理論から模索した。彼の理論には、企業のことを「私的な人格を否定した資金そのもの」とあるという認識であったが、この彼の見解を基盤にして、それを一部修正することによって、今日のNPO会計の問題解決および営利企業会計とNPO会計との統一化の可能性も見だせることを提案したのである。 ところで、最近わが国では、既存のNPO法人(とりわけ公益法人)の非効率な経営実態など、様々な問題点が指摘されているところである。こうした問題点を改善するために、公益法人会計の中にも営利企業会計の考え方を導入しようとして、公益法人の会計基準も改訂作業が進められているところである。本来、企業会計は、資本主義社会における営利企業の発展に伴って確立されてきたものであり、また「一期間における費用と収益との適切な対応」させることを根幹においている。この考え方を公益法人会計にも適用することは、公益法人の管理者に対し、経営資源の有効的活用、効率的経営の実施を意識づけるのに役立つと期待されているのである。つまり、企業会計は営利企業のみならず、公益法人等NPOにとってもまた有用であるとする見解が台頭してきたのである。 ただし、単純に既存の公益法人会計に企業会計方式を導入することはできない。株主が存在しない公益法人の「資本」概念をいかに確立するかという点があげられる。ちなみに、日本の公益法人会計改革において、前例として参考にしたアメリカ会計では、この課題に直面して、結局のところ株主の存在という点だけを必要以上に重視してしまい、NPO会計改革が不十分なものに終わってしまった。そこで、われわれの研究では、アメリカの失敗のケースも踏まえ、株主という存在も、組織体への資源提供者の一つの種類にすぎないと捉えることによって、公益法人にも営利企業における資本に相当するものの存在を認め得ることと提案したのである。こうしたわれわれの提案は、公益法人会計と営利企業会計との統一化を前進に寄与するものと考えている。 さらに、わが国のNPO会計における具体的問題点の一つとして、学校法人会計もとりあげた。この中でとりわけ、学校法人会計の計算体系が、企業会計のそれとは大きく異なり、この学校法人会計の計算システムでは、固定資産の不必要な取得を誘発する等の問題点を指摘し、こうした点からも前述の公益法人会計のみならず、全てのNPO会計において、企業会計と統一した枠組みの中で捉えることの必要性を指摘したのである。
CopyMonitor
学位論文、エッセー、その他文章を含む原稿を作成している方が対象となっております。著者の皆様の研究資料原稿を、CopyMonitorのデータベースおよびご自身の原稿と比較し、類似度チェック結果を確認することで、原稿に正しい引用表記および意図しない剽窃がないかをご提出の前にご確認いただけます。(学内教職員のみ)
お問い合わせ先
羽衣国際大学 学術情報・地域連携課
(平日 09:00~17:00 / 土曜 09:00~12:30)
〒592-8344 大阪府堺市西区浜寺南町1-89-1
研究活動
羽衣国際大学には2つの附置研究所と
教員及び学生の研究発表の場として
2誌の定期刊行物があります。
定期刊行物はいずれも全国の関係教育機関、
主要図書館で閲覧が可能ですが、
ここでは過去にさかのぼって、
両誌の目次とサマリーをご紹介しています。
詳しい内容をご希望のかたは、
羽衣国際大学「学術情報・地域連携課」まで
お問い合わせください。
附置研究所
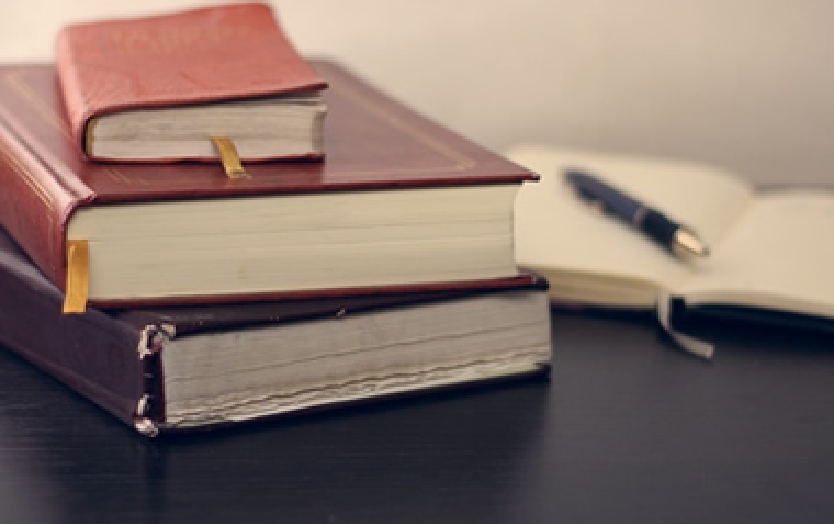
産業経営研究所
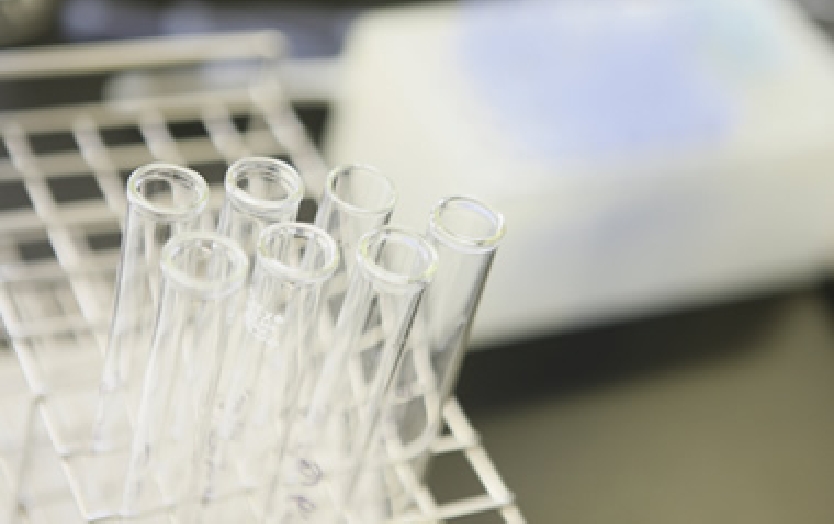
人間生活総合研究所
研究紀要:現代社会学部
現代社会学部教員の論文・研究ノート等の研究成果、学生の卒業論文・作品なども掲載しています。
研究紀要:人間生活学部
人間生活学部教員の論文・研究ノート等、研究成果を掲載しています。
産学官連携
お問い合わせ先
羽衣国際大学 学術情報・地域連携課
(平日 09:00~17:00 / 土曜 09:00~12:30)
〒592-8344 大阪府堺市西区浜寺南町1-89-1